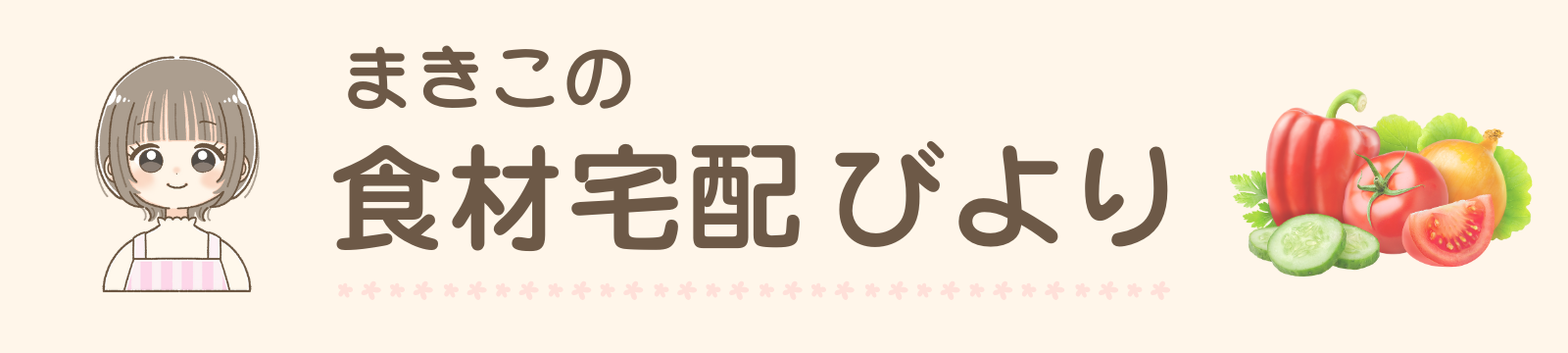「野菜を新鮮なまま保ちたいのに、すぐに使い切れない」と悩んでいる人は多くいます。新鮮な野菜を無駄にせずに長持ちさせるためには、冷凍保存が効果的です。この記事では、冷凍保存できる野菜とできない野菜、冷凍保存のメリット、保存方法、解凍方法を詳しく解説します。
記事を読めば、野菜の鮮度や栄養素を保つ冷凍保存方法がわかり、食品の無駄をなくせます。野菜を冷凍保存し、毎日の調理を効率化しましょう。
冷凍保存できる野菜・できない野菜

野菜には、冷凍保存できる野菜とできない野菜があります。それぞれの野菜について、詳しく解説します。
冷凍保存できる野菜
冷凍保存できる野菜は、冷凍しても風味や栄養を損ないません。長期保存でき、食材が無駄にならないため経済的です。以下の野菜は、冷凍保存が可能です。
- ブロッコリー
- ほうれん草
- ニンジン
- キャベツ
- カリフラワー
- ピーマン
- オクラ
- しいたけ
- トウモロコシ
- 枝豆
冷凍保存できる野菜は、必要なときにすぐに利用でき、調理時間を短縮できます。冷凍保存が可能な野菜を把握しておくと、買い過ぎた場合や旬の時期に安く買った野菜も無駄になりません。
» 新鮮でおいしい!野菜宅配がおすすめな理由と自分に合ったサービスの選び方
冷凍保存できない野菜
冷凍によって、食感が変化したり組織の細胞が壊れたりする野菜は、冷凍保存できません。冷凍保存できない野菜は、以下のとおりです。
- レタス
- キュウリ
- セロリ
- トマト(生のまま)
- ジャガイモ(生のまま)
- ナス(生のまま)
- サラダ菜
- アボカド(生のまま)
レタスやキュウリは、冷凍すると水分がなくなり、シャキシャキとした食感が失われます。トマトやジャガイモは、冷凍時に水分が膨張し、解凍後に組織の細胞が崩れます。冷凍保存できない野菜は、できるだけ早く食べましょう。冷凍保存できない野菜を把握しておくと、献立が立てやすくなり、新鮮な状態で消費できます。
野菜を冷凍保存するメリット

野菜を冷凍保存するメリットは、以下のとおりです。
- 長期間保存できる
- 調理時間を短縮できる
- 節約できる
長期間保存できる
冷凍保存は、野菜の鮮度を長期間保てます。冷蔵保存よりも長く保存できるため、必要なときにすぐ利用できるメリットがあります。食材が無駄にならず、計画的に消費でき、買い過ぎた場合も長期間保存できるので経済的です。冷凍保存は、鮮度を保った状態で保存できるため、季節に関係なく旬の野菜を楽しめます。
調理時間を短縮できる
あらかじめ食材のカットや下処理をして冷凍保存すると、調理時間を短縮できます。冷凍保存した野菜は、必要な分だけ取り出せるため、食材も無駄になりません。冷凍保存した野菜は短時間で火が通りやすく、忙しい日でも簡単に料理ができます。
解凍後、すぐ料理に使用したい場合は、野菜を薄くスライスしたり細かく刻んだりして冷凍すると便利です。
節約できる
野菜の価格は、天候や収穫量によって左右されます。価格が安定しているときや旬の時期に、野菜をまとめ買いして冷凍保存すると節約につながります。冷凍保存すれば買い物の頻度も減らせるため、時間や交通費の節約にも効果的です。
» まとめ買いで得する方法!まとめ買いにおすすめな商品や得するコツを紹介
冷凍できる野菜の保存方法と保存期間

冷凍保存できる野菜の保存方法と保存期間は、野菜の種類によって異なります。野菜の分け方は、以下のとおりです。
- 葉物野菜
- 根菜
- 果菜
- その他の野菜
野菜の種類別の保存方法と保存期間を詳しく解説します。
葉物野菜
ほうれん草や小松菜などの葉物野菜は、冷凍すると長期間保存が可能です。下茹でして冷凍保存すれば、野菜の色が鮮やかになり、鮮度を長く保てます。茹でた後は、しっかりと水気を切り、ラップや保存袋で小分けにして保存しましょう。使いたい分だけ取り出せて便利です。冷凍保存で鮮度と栄養を保てる期間は、約1か月です。
加熱料理やスープに直接入れると手間がかからず、調理時間を短縮できます。
根菜
根菜は、冷凍保存すると調理効率が良くなり、長期間保存できます。根菜を冷凍保存する手順は、以下のとおりです。
- 適当な大きさにカットする
- 下茹でして水気を切る
- 空気を抜いて袋に入れて冷凍保存する
保存期間は約1か月ですが、しっかりと冷凍できていれば、より長く鮮度を維持できます。加熱調理や自然解凍で使用すると、根菜の風味を損なわずにおいしく食べられます。根菜の冷凍保存は、栄養を損なわずに、調理時間や手間を省けるため、おすすめです。
果菜

トマトやナスなどの果菜は、冷凍保存に適しています。冷凍によって野菜の水分が凍ると、野菜の細胞が壊れにくくなるため、鮮度を維持できます。スライスまたはカットして冷凍保存しましょう。保存期間の目安は、約1か月です。使用時は、冷凍のまま調理するか、必要に応じて解凍してから使います。
果菜の中でも、ピーマンやキュウリは冷凍すると食感が変わるため、注意しましょう。シャキシャキとした食感が失われ、味が悪くなる可能性があります。毎日の食事作りを楽にしたり、料理の幅を広げたりするために、果菜の冷凍保存を上手く活用してください。
その他の野菜
その他の冷凍保存に適した野菜には、アスパラガスやブロッコリー、カリフラワー、とうもろこし、セロリなどがあります。冷凍保存方法は、以下のとおりです。
- アスパラガス
- 下茹でしてから冷凍すると、食感を保ちやすくなります。好みの長さにカットし、ラップで包んで冷凍保存します。
- ブロッコリーとカリフラワー
- 小房に分けて下茹でしてから冷凍すると、必要なときすぐに使用可能です。ラップでくるみ、冷凍袋に入れるか、冷凍保存容器に入れましょう。
- とうもろこし
- 下茹で後に粒を外して冷凍すると使いやすくなります。ラップで包んで冷凍保存します。
- セロリ
- 冷凍すると香りが飛んでしまうため、他の野菜と一緒に調理するのがおすすめです。みじん切りにして冷凍すると、スープや炒め物で使いやすくなります。
保存期間の目安は、約1か月です。1回の調理で使用する量の少ない野菜でも、冷凍保存すると、長期間使用できます。スープやサラダなどのさまざまな料理に加えられるため、料理のバリエーションが増え、食費も節約できます。
» 野菜不足を解消する方法4選!野菜嫌いな人におすすめな解消法も3つ紹介
野菜を冷凍保存するときのコツ

野菜を冷凍保存するときのコツは、以下のとおりです。
- 小分けにして保存する
- 必要に応じて下処理を行う
- 水分は拭き取っておく
- できるだけ早めに冷凍保存する
- チャック付きポリ袋や密閉容器に入れる
- 空気をしっかり抜く
- 急速冷凍する
小分けにして保存する
野菜を冷凍保存する際は、小分けにして保存すると、必要な分だけ取り出して使用できます。1つの袋に野菜を冷凍保存すると、解凍時にすべて使い切る必要があるため、野菜を無駄にしてしまう可能性があります。小分けにする前に、野菜を使いやすいサイズに切っておくと、必要なときにすぐ使用できて便利です。
小分けでの保存には冷凍焼けを予防する効果もあり、野菜の鮮度を維持できます。野菜を無駄にせず、長期間おいしさを保つためには小分け保存がおすすめです。
必要に応じて下処理を行う
野菜を冷凍保存する際は、必要に応じて下処理をする必要があります。適切に下処理をすると、野菜の鮮度を維持した状態で冷凍保存できます。主な下処理は、以下のとおりです。
- 野菜を洗って汚れを落とす
- 皮をむく
- 食べやすい大きさに切る
- 下茹でする
- 冷水で冷やす
野菜の下処理をすると、より長く鮮度を維持した状態で冷凍保存できます。野菜の鮮度を保ったり、使用時の手間を省いたりできるため、なるべく下処理をしましょう。
水分は拭き取っておく
冷凍保存する際は、野菜の水分をしっかり拭き取ってください。水分が残っていると、霜がつきやすくなったり、野菜同士がくっついたりして、食感や風味が損なわれます。野菜の中でも、葉物野菜は水分が多いため、しっかりと水分を拭き取りましょう。水分を拭き取るときは、厚手のキッチンペーパーがおすすめです。
できるだけ早めに冷凍保存する

野菜は時間の経過に伴い、鮮度や栄養価が低下するため、できるだけ早めに冷凍保存する必要があります。新鮮な状態で冷凍すると、野菜の風味や食感を維持できます。野菜が傷みそうになってから冷凍しても、おいしく食べられないため、注意してください。
» 栄養バランスの大切さを知るために!食事について完全解説
野菜は、冷凍されるまでの時間が短いほど、鮮度を保てます。金属性のトレーに乗せると早く冷凍できるため、活用してください。
チャック付きポリ袋や密閉容器に入れる
野菜を冷凍保存する際は、チャック付きポリ袋や密閉容器に入れると、冷凍庫内に臭い移りせず、衛生的に野菜を保存できます。食材は平らにすると素早く冷凍でき、短時間で解凍できます。冷凍庫のスペースを有効に活用したい場合は、チャック付きポリ袋がおすすめです。
密閉容器は、液状のものや汁気のある野菜の保存に適しています。保存期間を一目で確認できるように、ポリ袋や容器に日付を記入しましょう。容器に日付を記入する際は、マスキングテープがおすすめです。
空気をしっかり抜く
食材が空気に触れると、酸化します。酸化は、食材の風味や栄養を劣化させるため、袋の空気はしっかり抜いて密閉してください。チャック付きのポリ袋や密閉容器を使用すると、簡単に空気を抜けます。空気をしっかり抜くための手順は、以下のとおりです。
- 手で空気を押し出す
- ストローで空気を吸い出す
- 水に沈めながら密閉する
真空パック容器を利用すると、より簡単にしっかりと空気を抜けます。空気が残らないように密閉しましょう。
急速冷凍する
急速冷凍は、野菜の細胞組織を壊しにくく、食材の風味や食感を損ないにくいため、解凍後の品質が保たれます。一般的な解凍よりも解凍後のドリップが少ないのも特徴です。専用の急速冷凍機は、商業用食品保存に使用されていますが、最近では家庭用でも急速冷凍機能を備えた冷蔵庫が増えています。
急速冷凍機能がなくても、冷凍庫を低温で設定すれば、急速冷凍に近い効果が得られます。
冷凍した野菜の解凍方法

冷凍した野菜をおいしく食べるためには、解凍方法が重要です。冷凍した野菜の解凍方法は、以下のとおりです。
- 下茹でした野菜は流水で解凍する
- 生で冷凍した野菜は加熱して解凍する
- おろし・刻み野菜は自然解凍する
下茹でした野菜は流水で解凍する
下茹でした冷凍野菜を解凍するときは、流水を使用します。流水を使用するメリットは、以下のとおりです。
- 野菜本来の風味を保てる
- 食感が保ちやすくなる
- 鮮やかな色合いを保てる
解凍するときは、冷凍した保存袋のままボウルに入れ、流水をボウルに入れます。長く流水に入れると味が落ちるため、半解凍になったら取り出してください。流水の代わりに氷水を使用すると、味が落ちにくくなりますが解凍までに時間がかかります。流水解凍する前に、袋のチャックがしっかりと閉じているか確認しましょう。
生で冷凍した野菜は加熱して解凍する
生で冷凍した野菜は、加熱して解凍します。冷凍した野菜をそのまま加熱すると、解凍の際に水分が抜けにくくなり、栄養価を失わずに食べられます。素材の風味を損なわず、冷凍庫から取り出してすぐに使用できるため、調理時間が短縮されます。
凍ったまま焼く、蒸す、煮る、揚げるなど、さまざまな方法で加熱できるため、生の野菜を冷凍しておくと、便利です。電子レンジでの解凍も可能ですが、野菜の質を低下させる恐れがあるため、注意してください。電子レンジは、加熱ムラが生じやすいため、途中で混ぜたり、向きを変えたりしながら解凍しましょう。
おろし・刻み野菜は自然解凍する
おろし・刻み野菜は、自然解凍がおすすめです。自然解凍すると、食材の風味が保たれ、野菜が柔らかくなるのを防げます。冷蔵庫で時間をかけて解凍すると、食材の品質を維持できます。時間に余裕がない場合は、常温で解凍可能です。常温で解凍する場合は、風通しの良い場所を選びましょう。
まとめ

冷凍保存は、野菜を長期間保存できる方法です。野菜の冷凍保存には、調理時間を短縮したり食品の無駄を削減したりするメリットがあります。冷凍保存前の適切な下処理方法は、野菜の種類ごとに異なります。下茹でやカットなど、野菜に適した下処理をしましょう。
冷凍保存する際は小分けにして水分を拭き取り、チャック付きのポリ袋や密閉容器に入れると鮮度を保てます。冷凍野菜を解凍する主な方法は、流水解凍と加熱解凍、自然解凍の3つです。野菜に合った方法で解凍すると、鮮度や栄養素を維持でき、おいしく食べられます。
冷凍保存を活用して、野菜を無駄なく使い切りましょう。