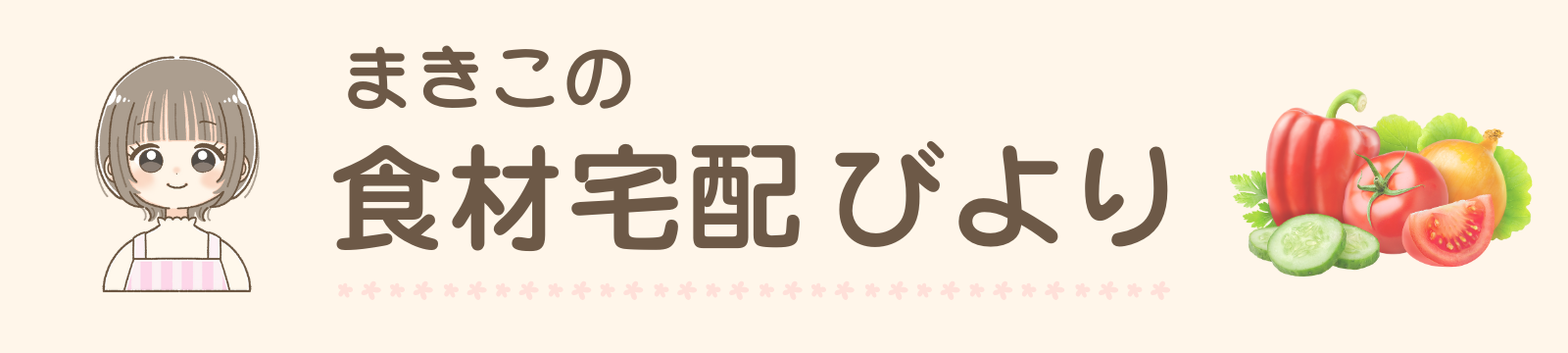ナッツは健康的な食生活におすすめの食品ですが、効果的な食べ方や選び方がわからない方は多くいます。この記事ではナッツの効果的な食べ方や適切な摂取量、栄養、健康効果を徹底解説します。記事を読めば食生活に無理なくナッツを取り入れる方法がわかり、上手な活用が可能です。
ナッツの1日の摂取量は20~30gが目安で、間食や朝食で取り入れることがおすすめです。ナッツの風味や食感を生かして料理に活用することもできます。
ナッツの効果的な食べ方

ナッツの栄養効果を最大限に引き出すには、食べるタイミングや摂り方が大切です。ナッツの効果を引き出す食べ方は以下のとおりです。
- 間食として食べる
- 朝食に取り入れる
- 料理に活用する
間食として食べる
ナッツは小腹が空いたときの間食にぴったりな食品です。ナッツは満足感が高く、空腹を効果的に抑えられるためです。ナッツには血糖値の急上昇を緩やかにする効果もあるため、長時間エネルギーを持続させ次の食事までの空腹感を和らげてくれます。
間食にナッツを摂取する際は、1回当たり片手に軽くのる程度(約30g)が目安です。ナッツを単独で食べる以外にも、ドライフルーツやヨーグルトに混ぜる食べ方もあります。ナッツを小分けにして持ち歩くと、外出先でも手軽に摂取できます。
間食用には生のナッツか塩・油・糖分無添加の素焼きナッツを選びましょう。添加物の少ないものを選ぶことで、より健康的に栄養を摂取できます。夕食前の軽い間食としてナッツを食べると、食べ過ぎを防止する効果も期待できます。
朝食に取り入れる

ナッツは良質な脂質とタンパク質を含むので、朝食に適しています。朝食にナッツを取り入れると1日のスタートから栄養バランスが整い、効果的にエネルギーが補給できます。ナッツをオートミールに混ぜたり、ナッツバターをトーストに塗ったりなどさまざまな食べ方が可能です。
ナッツとヨーグルトは相性がよく、ヨーグルトにナッツとはちみつを加えるだけで栄養バランスの取れた朝食が作れます。ナッツは調理不要で食べられるので、手軽に栄養を追加できる点も魅力です。パンケーキやワッフルの生地にナッツを混ぜ込んだりマフィンに入れたりすると、手の込んだ朝食が作れます。
料理に活用する
ナッツを料理に活用すると、栄養価を高めながら風味や食感を楽しめます。ナッツをサラダや炒め物、スープに加えるとナッツの食感を味わえます。砕いたナッツを肉や魚にまぶせば、揚げ物の衣として活用が可能です。
ナッツはお米との相性も良く、炊き込みご飯や雑穀米に加えれば香ばしさがプラスされます。スイーツや焼き菓子の材料に加えると、風味と食感が豊かになります。
自家製ナッツバターを作るのもおすすめです。手作りすることで添加物を減らしたり、甘さを調節したりできます。好みのナッツをフライパンやオーブンでローストして、フードプロセッサーでかくはんしたら完成です。はちみつやメープルシロップで甘さを加えましょう。パンのトッピングや料理の隠し味として楽しめます。
ナッツの適切な摂取量

ナッツは栄養が豊富ですが、カロリーも高いため適量を守ることが重要です。ナッツの適切な摂取量について以下の3つを解説します。
- 1日に食べるナッツの目安量
- 食べ過ぎのリスク
- 適量を守るためのコツ
1日に食べるナッツの目安量
日本人の場合、1日に摂取するナッツの理想量は20〜30g程度です。ナッツの種類ごとの摂取量目安は以下のとおりです。
| ナッツの種類 | 目安量 |
| アーモンド | 約23粒 |
| クルミ | 7〜8粒 |
| カシューナッツ | 約15粒 |
| マカダミアナッツ | 約10粒 |
ナッツはカロリーが高いため、体重管理をしている方はカロリー計算に含めるようにしてください。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、明確なナッツの推奨量は示されていません。個人の体重や活動量、健康状態によって摂取量を調整しましょう。
食べ過ぎのリスク

ナッツは健康に良い食品ですが、食べ過ぎるとさまざまな問題が生じる可能性があります。ナッツは良質な脂肪を含みますが、100g当たりのカロリーは約600kcalです。ナッツ100g当たりのカロリーはご飯100gの約2倍に相当するため、食べ過ぎによるカロリー過多に注意が必要です。
クルミやピーナッツ、アーモンドにはオメガ6脂肪酸が多く含まれます。オメガ6脂肪酸を過剰に摂取すると、体内の炎症反応を促進する場合があります。有塩ナッツは塩分の過剰摂取の恐れがあるため、無塩ナッツを選びましょう。
アレルギーを持つ方や腎臓病の方はナッツの摂取量に注意しましょう。ナッツにはリンやカリウムが含まれており、重篤な反応を引き起こす危険性もあるため注意が必要です。
» 日本人の1日の塩分摂取量と減塩のコツ
適量を守るためのコツ
適量のナッツを摂取するために、計量スプーンやキッチンスケールを使用して正確な量を測りましょう。片手にのせたナッツの量が約30gなので、慣れてきたら手のひらを使った目測も可能です。
ナッツの食べ過ぎを防ぐためには、料理のトッピングにしたりオートミールに混ぜたりしましょう。1日分のナッツを小分けにして、保存容器やジップ付き袋に入れておくと適量を守りやすくなります。食べる時間を決めたり、アプリで摂取量を記録したりする方法も効果的です。
ナッツの栄養と健康効果

ナッツには複数の栄養素が含まれており、健康効果が科学的に裏付けられているものもあります。ナッツに含まれる以下の栄養素と得られる健康効果について解説します。
- 不飽和脂肪酸
- ビタミン・ミネラル
- タンパク質
- 食物繊維
不飽和脂肪酸
不飽和脂肪酸はナッツに含まれる重要な栄養素の一つです。不飽和脂肪酸の中でも、オメガ3脂肪酸(αリノレン酸)とオメガ6脂肪酸(リノール酸)は「必須脂肪酸」です。必須脂肪酸は体内で合成できないため、食事からの摂取が欠かせません。不飽和脂肪酸の健康効果は以下のとおりです。
- 悪玉コレステロール減少
- 善玉コレステロール増加
- 心血管疾患リスク低減
- 慢性炎症抑制
- 認知機能向上
- 細胞膜の柔軟性維持
- ホルモン生成
オメガ3脂肪酸はクルミに多く含まれており、オメガ6脂肪酸はアーモンドやカシューナッツに多く含まれています。必須脂肪酸ではありませんが、アーモンドやカシューナッツには不飽和脂肪酸のオレイン酸(オメガ9)も含まれます。
ビタミン・ミネラル
ナッツにはビタミンとミネラルが豊富に含まれており、不足しがちな栄養素を効率よく摂取できます。ナッツに含まれる主なビタミンとミネラルは以下のとおりです。
- 亜鉛
- 免疫機能を強化し、細胞の修復や再生をサポートします。
- マグネシウム
- 骨の健康維持や筋肉機能の正常化、血圧調整に重要な役割を果たします。
- カリウム
- 血圧調整や神経伝達、筋肉機能の維持に必要です。
- セレン
- 甲状腺機能の調整や抗酸化作用に関与します。
- リンやマンガン、銅
- 骨の形成や酵素の活性化をサポートします。
- ビタミンE
- アーモンドやヘーゼルナッツに多く含まれ、強力な抗酸化作用があります。ビタミンEは体内の活性酸素から細胞を守る働きがあるため、若々しさを保つために欠かせません。
- ビタミンB群(B1やB2、B6、葉酸など)
- 代謝を促進し、エネルギー産生をサポートします。
ナッツを摂取したときのビタミンやミネラルの吸収率は、生のナッツよりもローストしたナッツの方が高い場合があります。ただし過度の加熱は栄養素を損なう可能性があるので、軽くローストしたものを選びましょう。
タンパク質

ナッツには良質な植物性タンパク質が含まれます。ナッツに含まれる植物性タンパク質は100g当たり約15〜20gです。アーモンドやカシューナッツは100g当たり約21gと高タンパク質です。植物性タンパク質は、動物性タンパク質より消化吸収がゆるやかな特徴があります。
植物性タンパク質は血糖値の急激な上昇を防いだり、満足感が持続したりする効果が得られるため、ダイエットにも活用可能です。ナッツのタンパク質は、穀物類と組み合わせることで質が向上します。ナッツバターなどの加工品でもタンパク質を摂取できます。
ナッツは運動後の回復食としても適しており、高齢者の筋肉量維持にも有効です。必須アミノ酸もバランスよく含まれるため、ベジタリアンやビーガンの方の貴重なタンパク質源にもなります。
食物繊維
ナッツは食物繊維を豊富に含み、100g当たり約5〜10gが含まれます。食物繊維を多く含むナッツはアーモンドとピスタチオです。ナッツに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌の増殖を促し、健康的な腸内フローラを形成するのに役立ちます。
ナッツには水溶性と不溶性の食物繊維がバランスよく含まれています。腸の働きを総合的にサポートし、腸内環境を改善するため便秘の予防・改善にも効果的です。
» 栄養バランスのとれた食事を実現する方法!
ナッツの種類別の栄養と健康効果

ナッツには種類によって栄養素と健康効果が異なります。以下のナッツの栄養と健康効果を解説します。
- アーモンド
- クルミ
- カシューナッツ
- マカダミアナッツ
- ピーナッツ
アーモンド
アーモンドはナッツ類の中でも栄養価が高く、良質な不飽和脂肪酸を豊富に含みます。抗酸化作用を持ち、老化防止に効果のあるビタミンEや、骨の健康維持に役立つマグネシウムやカルシウムも含まれます。アーモンドのタンパク質含有量は100g当たり約21gと、他のナッツより多い傾向です。
アーモンドは皮付きで食べると抗酸化物質やフラボノイドをより摂取できるので、皮ごと食べるのがおすすめです。
クルミ
クルミは他のナッツ類と比較して、オメガ3脂肪酸(α-リノレン酸)が圧倒的に豊富に含まれます。クルミに含まれる栄養素は以下のとおりです。
- オメガ3脂肪酸
- ビタミンE
- 葉酸
- マグネシウム
- リン
- 銅
クルミは脳の健康をサポートし、脳機能の向上や認知症予防に効果があります。クルミに含まれる抗酸化物質や植物性ステロールが脳内の炎症を抑え、神経細胞を保護するためです。クルミは独特の形状と風味があり、料理で活用しやすい点も魅力です。
カシューナッツ

カシューナッツは独特のクリーミーな食感と軽い甘みが特徴のナッツです。カシューナッツはウルシ科の木の実で、厳密には種子にあたります。他のナッツ類と比べて低脂肪でありながら、良質なタンパク質を多く含んでいるのが特徴です。
カシューナッツには、銅やマグネシウムなどのミネラルや不飽和脂肪酸が含まれます。最近では植物性食品への関心の高まりから、カシューミルクやカシューチーズなどの代替食品としても注目されています。生のカシューナッツには皮膚刺激物質が含まれるため、市販のカシューナッツはすべて加熱処理済みです。
» 脂質の働きと1日の健康的な摂取目安量を解説
マカダミアナッツ
マカダミアナッツは、なめらかな食感と濃厚な風味で知られる高級ナッツです。マカダミアナッツは脂質含有量(70〜80%)が高く、脂質の大部分は不飽和脂肪酸のオレイン酸が中心です。マカダミアナッツには貧血を予防する鉄や銅も含まれます。
マカダミアナッツは低GI食品でもあるため、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。高カロリーですが、少量でも満足感を得られるため食事管理にも有効です。
ピーナッツ
ピーナッツは他のナッツ類と異なり、マメ科に分類される食品です。良質な植物性タンパク質で、100g当たり約25~28gものタンパク質が含まれます。ピーナッツの渋皮には、ポリフェノールの一種のレスベラトロールが含まれます。レスベラトロールは抗酸化物質で、抗炎症・抗酸化作用が期待される成分です。
ピーナッツには不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、心臓病リスクを低減する効果があります。ピーナッツは低GI食品なので、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。ピーナッツは他のナッツ類に比べて比較的安価で入手可能です。アレルギーのある方は、摂取に十分注意してください。
ナッツの効果的な保存方法

ナッツは栄養価が高い食品ですが、保存方法を間違えると酸化により風味や栄養素が低下します。ナッツの効果的な保存方法について以下2点を解説します。
- 酸化を防ぐ保存方法
- 冷蔵・冷凍保存のコツ
酸化を防ぐ保存方法
ナッツを保存する際は、酸化を防ぐことが大切です。ナッツに多く含まれる不飽和脂肪酸により酸化しやすいためです。ナッツが酸化すると風味が落ちるだけでなく、健康効果も減少します。ナッツの保存方法は以下のとおりです。
- 密閉容器を使用する
- 脱酸素剤を利用する
- 小分けにして保存する
- 殻付きのまま保存する
- 湿気・直射日光を避ける
- 強い匂いの食品から離す
保存容器はジップ付き袋や密閉性の高いガラス容器がおすすめです。焙煎したナッツは生のナッツよりも酸化しやすいので注意が必要です。鮮度を保つために、購入後はなるべく早めに食べきりましょう。
冷蔵・冷凍保存のコツ
ナッツを長持ちさせるには、冷蔵庫や冷凍庫での保存が効果的です。冷蔵保存の場合は1〜3か月、冷凍保存なら6か月〜1年、ナッツの品質を保てます。保存には密閉容器を使用し、小分けにして冷凍しましょう。高密閉度の容器を選ぶと、より湿気を防ぎながら保存ができます。
ナッツを冷凍保存する場合は、脱酸素剤を一緒に入れると酸化防止効果がさらに高まります。ローストしたナッツは生のものより酸化しやすいので、保存期間が短くなる点に注意しましょう。冷凍したナッツは特別な解凍作業が不要で、冷凍のまま料理に使えます。
常温に戻す際はナッツを袋や容器から出さずに、室温にゆっくりと戻すようにしましょう。急激な温度差で袋の内側に結露が生じるのを防ぐため、常温に戻ってから開封するのがポイントです。
まとめ

ナッツは健康的な食生活を送るために活用しやすい食品です。ナッツは間食や朝食、料理に取り入れるなどの食べ方があります。ナッツには不飽和脂肪酸やビタミン・ミネラル、タンパク質や食物繊維などの栄養素が含まれます。
ナッツの種類により含まれる栄養素が異なるため、複数の種類を組み合わせて食べるのもおすすめです。1日20〜30g程度の適量を守ることで、栄養素をバランス良く効率的に摂取できます。ナッツは高カロリーであるため食べ過ぎには注意しましょう。
ナッツの栄養価を保つためには保存方法も重要です。酸化を防ぐために密閉容器に入れ、長期保存する場合は冷蔵・冷凍保存がおすすめです。ナッツを効果的に取り入れて、健康な食生活を送りましょう。
» 体に良い食べ物と悪い食べ物|健康的な食生活を実現しよう!